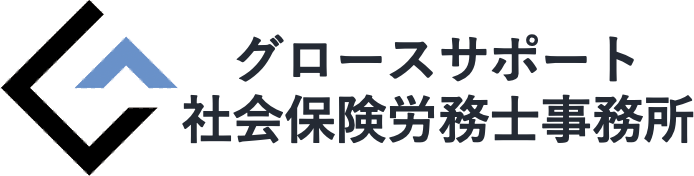なぜあの会社は採用がうまくいくのか?
知名度が低くても会社規模が小さくても採用がうまくいく秘訣とは

新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。
本年も皆様の益々のご発展を心より祈念しております。
さて、本日は新卒採用について皆様に是非お伝えしたいことを書いていきます。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
少子高齢化の現在、新卒採用の厳しさは年を追うごとに増しています。東京商工会議所の「2024年新卒者の採用・選考活動に関する調査」によると、計画以上の内定者数を確保している企業は14.5%にとどまり、充足率(採用予定人数に対する実際に採用できた人数の比)が50%未満の企業は前年同時期の33.0%から41.5%に増加しています。また、充足率0%の企業も10.2%から16.0%へ増加しており、これまで以上に新卒採用が厳しい状況にあることが分かります。
また、マイナビのまとめた「マイナビ 2025年卒企業新卒内定状況調査」では、25年卒の採用充足率は70.0%で、3年連続の減少、過去最低となっています。更に、約3割の企業で、すでに2024年新卒入社社員の退職が出ていることが分かりました。
「大転職時代」と呼ばれる今日、約3割の新入社員は入社時点から「数年たったら転職するつもり」で入社しているという調査結果もあります。
そんな状況の中、採用がうまくいく企業とそうでない企業の別れ目は一体何でしょうか?
「あそこは採用にかける予算がふんだんにあるから」答えはノーです。
「うちは田舎の中小企業だから大企業にはかなわない」これもノーです。
「うちは若者受けする業界じゃないから」そんな事はありません。
中小企業が採用で憂き目を見るのは、大企業1人勝ちの「母集団市場主義」のレッドオーシャンに身をおいてしまっているからです。母集団至上主義とは、「望む人材の確保には、とにかく沢山の人を集めることだ」という発想のもと、「リクナビ」や「マイナビ」など、多くの学生が登録する採用メディアに自社の情報を掲載し、できるだけ多くの母集団を集めることに必死になっている状態を示します。
無名の中小企業が採用で勝つためには、「母集団市場主義」を捨て、自社の「強み」を一貫したコンセプトとして伝えていくことが重要です。他社にはない「自社固有の強み」で採用に勝つ。ブルーオーシャンへのパスポートはまさにこの「採用ブランディング」の手法です。
「採用ブランディング」の考え方はここ5年ほどで急速に普及してきた考え方で、『自社の強みを、採用市場で直接、またはさまざまな媒体やツールを利用して、一貫性を持って伝えていく手法です』。コンセプトとして打ち出す自社の理念に共感できる人を採用するため、採用のミスマッチや就職後の離職率も低くなるばかりでなく、このような手法で入社してきた人材は「活躍人材」となり、会社に利益をもたらす人材に成長する可能性が非常に高くなります。また、自社の理念に共感して入社してきているので、出身校の後輩や友人に「うちの会社はやりがいがある」と勧めてくれ、リファラル採用に結びつくこともあります。
会社の成長エンジンはまさに「人」にありますが、そのような優秀な人材を採用することで、その人材の活躍により、結果的に企業の収益が向上し、企業の成長発展につながる、という良い循環が出来上がるのです。
では、採用ブランディングは実際にどのように進めれば良いでしょうか。
大まかにいうと、①自社の強みに基づいた採用コンセプトを策定し、②採用したい人物像を描いたペルソナを設定し、『③ターゲットに近い応募者を集め、④独自性のある選考フローを実施し、⑤フォローや教育を経てミスマッチの少ない採用を実現する』という流れとなります。
まずは、採用コンセプトの設定ですが、これは、一朝一夕にはできません。まず、自社独自の強みや良さを棚卸しするところからスタートします。そして、社風や企業理念、全社事業戦略などとも照らし合わせながら、策定していきます。この採用コンセプトは、その後、ナビ媒体への掲載、採用HP作成、パンフレット作成、インターンシップ、イベント、会社説明会、面接などの各採用フローに一気通貫して共通のイメージをもたらすものとなり、自社企業のブランドイメージを形成するものとなります。
例えば、従業員50名程度のある中堅税理士法人はこのコンセプトを「世代を超えて続く信頼。高いクオリティでクライアントとの絆を大切にしています」と定め、社内で行なっている徹底した品質管理やリスク管理、それにより、クライアントとの間に非常に厚い信頼関係を構築した結果、クライアント企業が親から子に代替わりしても、自社が親から子の代へと権限委譲しても、変わらずに続いていく信頼関係を表現しました。
その結果、理念に共感し覚悟を持った人材が入社したため、担当クライアントを持てるようになるまでの下積み時代も「真の実力をつけるために必要な時間」と捉えることができる忍耐力のある人材を確保することに成功し、早期離職の防止にもつながった例もあります。
次に、どのような人物を採用したいかを具体的に思い描き、ペルソナを設定します。
このペルソナ設定は具体的であればあるほど、役立つものとなります。
例えば、ある愛知のメーカーでは『名古屋工業大学のワンダーフォーゲル部の学生で、自宅から大学に通い、地元就職したいと考えている学生』と定義しました。このように、採用したい人物像であるペルソナが明確で具体的であればあるほど、応募者集めにおいて、的を絞りこめるため時間とコストの節約となります。
これまで100万円以上かけて、幾つものイベントに出ていたのが、ターゲットのいる大学が主催する合同説明会に出展するだけで良くなり、大幅なコスト削減に繋がったのです。
採用コンセプトと採りたい人物のペルソナ設定ができたら、あとは、採用の各フローに落とし込んでききます。ナビ媒体への掲載、採用HPの作成、SNSでの発信、イベント、企業説明会、インターンシップ、採用試験、面接、これら全ての工程において、先程の「コンセプト」と「ペルソナ」を基として戦略をたて、方針を決めることとなります。
採用難の昨今、巷には、採用関連のセミナーが溢れ、「人を惹きつける採用HP作成」「企業説明会成功の秘訣」「採用におけるSNS運用の鍵」など、時流に合わせた様々なトピックのセミナーが開催されていますが、多くは、採用フローの一部分だけを切り離して、小手先の技術的な話に終始しています。また、どの企業にも共通して使える技術は自社の独自性を現すものとはなりません。このようなことを学ぶのは勿論意味のないことではありませんが、最も重要なのは、自社の強みや想いを詰め込んだ「コンセプト」を全採用フローにおいて、一気通貫で表し自社ブランドのイメージを伝えることで、一つ一つの施策が共通した戦略に基づいていることです。
採用HPやSNS運用などある程度、テクニカルな造詣を必要とする部分はその道のプロである業者に任せる、というのも一つの手段ではありますが、その際は、業者に「コンセプト」をしっかりと伝え、全体を指揮監督する担当者をつける必要があります。業者任せにしていると、一番重要な採用コンセプトの部分に「Create the future whit us」など、一般的で抽象的なコピーライトをつけられてしまうことになります。
また、ナビ媒体への掲載文章の執筆はコピーライターのAに任せ、採用HPは業者Bに、SNS運用は業者C、採用パンフレットの制作は業者Dという具合だと、コンセプトの一気通貫どころか、全くテイストの揃わないものに仕上がってしまう可能性も出てきます。各採用ブローや採用に関わるマーケティングツールについても、表したいコンセプトがしっかりと浮かび上がるものになるよう、一つ一つ想いを込めて精緻に構築する必要があるのです。
そこで、よく聞かれるのが「いやいや、採用ブランディングなんて、ある程度規模のある会社さんの話でしょ。うちは、ハローワークと地元の小さなナビ媒体で募集するのがせいぜいだから」というような話です。それは全くの誤解です。
企業規模が従業員十人程度というような小さな企業こそ、自社ならではの「強み」で勝負する必要があるのです。採用ブランディングは何も大仰なものではありません。
ハローワークへの求人掲載一つとっても、その募集文章は自社の強みや理念をしっかりと表し、応募者の心に刺さるものになっているでしょうか?また、ターゲット像を描いたペルソナを基に本当に採用したい人材が応募してくるような、具体的な表現を盛り込んだものになっているでしょうか?申込み人数の欲しさあまりに、ていの良い当たり障りのない表現を書き連ねた結果、応募者はそこそこ来るけれど、いまいち、マッチする人材に出会えない、せっかく採用したのにすぐ辞めてしまう、といった事態になっていないでしょうか?
さらには、零細企業がコストを出来るだけかけずに募集する方法として、ハローワークや地元の小規模な求人サイトを選択しているのは分かりますが、掲載媒体としてそこが本当に妥当かどうか、検討したことはあるでしょうか?
例えば民間の広告媒体を使用する場合、採用したいターゲットがほとんどいない媒体に半年以上掲載料を払い、だらだらと採用を続けても、お金をドブに捨てるようなものです。採用したいターゲットが多く登録していそうな採用媒体をしっかりと見極め、1ヶ月の掲載で、良い人材が採用できれば、採用に費やす時間もコストも最小限に抑えることができます。
また、面接も応募者に自社の強みや理念を伝える重要な採用フローの一つです。
条件面であう・あわない、のふるいにかけることに必死になって、自社の良さを伝え、相手を見極める折角の貴重な時間を無駄にしてしまっていないでしょうか?あなたの会社が「何人か面接して一番良い人を採ろう」と思っているように、応募者も「数社受けて、一番感じの良いところ、自分にあいそうなところに決めよう」と考えているのです。面接で良い印象を与えられれば、応募者の中で志望度が急上昇し、本来ならもっと大手の企業に行ってもおかしくないポテンシャルの高い学生が他社の内定をけって、来てくれることもあるのです。その為には、面接会場の雰囲気から、面接官の立ち居振る舞い、その発する一言一言が採用コンセプトに根ざしたものとなっており、会社の理念や良さを最大限伝えるものとなっている必要があります。
さて、ここまで見てくると、採用に悪戦苦闘している小規模企業こそ、採用ブランディングの発想が必要であることが分かっていただけたかと思います。
いかがでしょうか?採用ブランディングは、欲しい人材を獲得し、ミスマッチを少なくする最強の採用手法です。
採用でお困りの方、本内容にご興味をお持ちの方は、是非お気軽に、グロースサポート社会保険労務士事務所にご連絡下さい。
参照:東京商工会議所「2024年新卒者の採用・選考活動に関する調査」「マイナビ 2025年卒企業新卒内定状況調査」
『知名度が低くても“光る人材”が集まる採用ブランディング』深澤了